学校から突然の呼び出し
次女、小2の2学期。
担任の先生から電話がありました。
「お話したいことがあるので、明日お時間いただけますか?」
悪いことで呼び出されたに違いない!
でも何も思い当たることがない…とびくびくしながら翌日学校へ。
話を聞くと、
「お友達のお母さんから “次女さんに言われたことで傷ついた” と連絡がありました」
とのこと。
たしかに次女は年齢より大人びた考えを持っていて、低学年の理解力では違う受け取られ方をしてしまうかもしれません。
でもそれは一度きりの発言で、担任によるとその後仲良く遊んでいるようだし、暴言や容姿についての発言でもなく、ケガさせたわけでもありません。
低学年ならよくあるやり取りでした。
それなのに、それまで親子で仲良くしてきた相手からすぐに学校へクレームが入ったことは、正直とてもショックでした。
実は「隠れモンペ」だった?
一見穏やかで普通に見えるママさんでも、ふとした出来事で「実はモンスターペアレント?」と思う瞬間があります。
今回の件で、申し訳ないけれどそのママさんは私の中で要注意人物リスト入りしました。(←怖)
そしてこれまでの経験や見聞きした話をふまえて、私が感じる 「隠れモンペ気質のママ友の共通点」 をまとめました。
あくまで私の価値観であり、否定ではなく「私はこういう人とは距離を置いた方が心地よく過ごせる」という目線です。
👇子供が自分で習い事に行くようになったら持たせると安心、見守りGPS
気を付けたいママ友の特徴4つ
①先生の悪評をツマミに盛り上がる
特に新年度に入ると、先生の悪評で盛り上がるママさんが増殖します。
正直、不満ばかりなら私立に転校すれば?と思います。
公立の先生だって一生懸命やっているし、一対一ではない以上、至らない点が出るのは当然。
でもモンペ気質の人は「先生のせい」「学校のせい」「お友達のせい」と他責にして、家庭内で話し合って解決法を考えようとしません。
もちろん、明らかにおかしな言動や子供の今後に支障がありそうなことをされた場合に「相談」するのは有りだと思いますが、噂や憶測をツマミに話すママさんは要注意。
②軽いノリですぐ学校に報告
少しの違和感でも、家庭内で解決法を考えずすぐ学校へ報告するタイプ。
今回の件もそうですが、子供同士で解決できていることに大人が介入することで、むしろ話がこじれる 場合があります。
もちろん深刻な内容なら学校に伝えるべきですが、
「ちょっと気になった」レベルまで学校に持ち込む必要はあるでしょうか?
小さなことでもクレームが入れば、先生は何かしらの対応を迫られ、事が大きくなってしまいます。
小2くらいなら、些細なトラブルは自分たちで解決する経験も大切だと感じます。
(もちろん子供によって時期の見極めは必要)
③いつも同じママ友グループでつるむ
学校行事や町内行事で、いつも同じメンバーで集まっているママさん。
話題は必然的にネタが尽きない先生や子供のことになり、
- 「あの先生問題あるよね」
- 「こんなことで学校に連絡した」
- 「それクレーム入れた方がよくない?」
と、互いに後押ししてモンペ化がエスカレートしてしまう傾向があるように感じます。
そしてクレーム内容自体がまたネタになる悪循環…。
④子離れできず、過保護
我が子がかわいいのは、どの親も一緒です。
ただし、成長に合わせて少しずつ親子の距離を取り、自分の力で生きる術を身につけさせることも大切です。
いつまでも親がレールを敷きすぎたり、大人の介入なしでは解決できない環境にしてしまうのは考えもの。
親の意識が子どもに向きすぎると「モンペ気質」が強まりやすいので、注意が必要です。
モヤモヤ発散方法
こちらが気を付けていても、理不尽なことは起こります。
でも今後も交流が続く相手に直接仕返しするのはタブー。
今回、私はだいぶ長い期間モヤモヤして眠りも浅かったですが、意識的にこんなことをして発散しました。
- ランニングや水泳をいつもより強度高めで取り組んだ
- 相手を知らないママ友に相談して話を聞いてもらった
これでモヤモヤの6割は解消!
こんな時に夢中になれる趣味があれば良かったけれど、今の私はそこまでないのですね…。
でも、運動はかなりのストレス発散になるのでおすすめです!
あと、いつかギャフンと言わせてやろうと、今まで以上に親子で英語学習に励もうと決めました。
まとめ
今回の体験で改めて思ったのは、
「一見普通に見えるママでも、実はモンペ気質のことがある」ということ。
個人的に、モンペママさんとは適度な距離を置くのが安心だと思います。
裏で何を言われてるかわからないのはとても気分が悪いのです…!!
子供同士の小さなトラブルは、時に成長のチャンスです。
すべてを親が解決するのではなく、子供に任せることも大切ですよね。
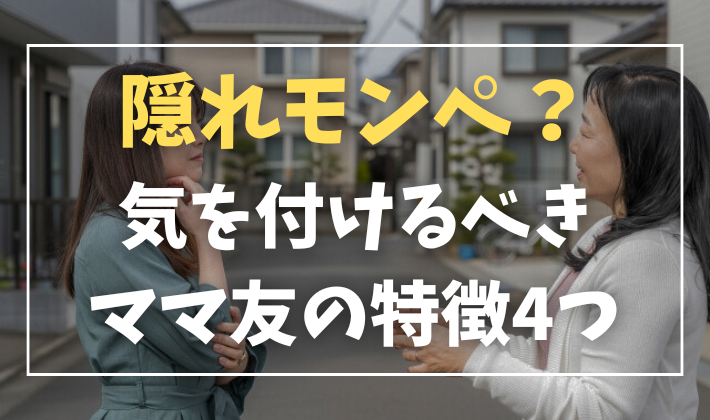

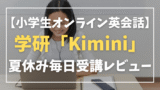
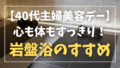
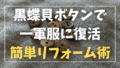
コメント